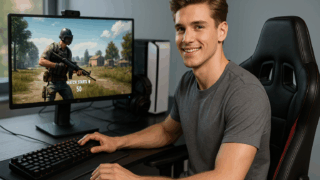スイッチボットカーテンのデメリットは?後悔しないための全知識
 「アレクサ、カーテン開けて」…声やスマホでカーテンを自動開閉できるSwitchBotカーテン。未来的なスマートホームへの憧れから導入を検討している方も多いでしょう。しかし、その手軽さの裏に潜むスイッチボットでカーテン開閉を自動化するデメリットについて、あなたは十分に把握していますか。スイッチボットでカーテン開閉を自動化するデメリットを知らずに購入し、後悔するのは避けたいですよね。
「アレクサ、カーテン開けて」…声やスマホでカーテンを自動開閉できるSwitchBotカーテン。未来的なスマートホームへの憧れから導入を検討している方も多いでしょう。しかし、その手軽さの裏に潜むスイッチボットでカーテン開閉を自動化するデメリットについて、あなたは十分に把握していますか。スイッチボットでカーテン開閉を自動化するデメリットを知らずに購入し、後悔するのは避けたいですよね。
「スイッチボットの欠点は何ですか?」と検索すると、「取り付けられないカーテンレールがある」「動作音がうるさい(キュルキュル音)」「途中で引っかかる」「両開きだと2台必要で割高」といった声が見つかります。SwitchBotがダメな理由、そして最新モデル(カーテン3や4の噂)で改善されているのか。この記事では、SwitchBotカーテン導入前に知っておくべきデメリットと、それを克服するための対策、そして後悔しない選び方まで、徹底的に解説します。
- 最大のデメリットは「対応カーテンレールの制限」
- 動作音(キュルキュル音)や途中で引っかかる可能性も
- 両開きカーテンには2台必要、ハブ(別売)がないと機能制限も
- 購入前に自宅のレール形状とカーテン重量の確認が必須
SwitchBotカーテンの落とし穴?デメリットと対策を徹底解剖
 「SwitchBotがダメな理由は?」とまで言われることもある、そのデメリットの真相に迫ります。取り付けられないケース、動作時のストレス、そして意外なコスト。導入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、ネガティブな側面もしっかりと理解しておきましょう。
「SwitchBotがダメな理由は?」とまで言われることもある、そのデメリットの真相に迫ります。取り付けられないケース、動作時のストレス、そして意外なコスト。導入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、ネガティブな側面もしっかりと理解しておきましょう。
- 最大の関門!「スイッチボット カーテン つけ られ ない」レール
- 動作音が気になる?「キュルキュル音」の正体
- スムーズに動かない?「引っかかる」「斜めになる」原因
- 意外なコスト?「両開き」と「ハブ」の必要性
- SwitchBotは中国企業?サポートやプライバシーは大丈夫?
1. 最大の関門!「スイッチボット カーテン つけ られ ない」レール
SwitchBotカーテン最大のデメリットであり、購入前に最も注意すべき点が、「対応するカーテンレールの種類に制限がある」ことです。SwitchBotカーテンは、既存のカーテンレールの上を自走してカーテンを開閉する仕組みです。そのため、特殊な形状のレールや、取り付けスペースが不足している場合には、物理的に設置できません。
公式サイトに対応レール(U型、I型、ポールタイプなど)の詳細な情報や、取り付け可否を判断するための測定ガイドが公開されていますが、それでも「うちのレールは微妙…」「測ってみたけど不安…」と感じるケースは少なくありません。特に、装飾性の高いレールや、カーブしているレール、天井埋め込み型のレールなどは、非対応である可能性が高いです。
また、レールの端(ランナーを引っ掛ける部分)の形状や、壁との距離なども取り付け可否に影響します。購入してから「つけられない!」となるのが最悪のパターン。「スイッチボット カーテン つけ られ ない」事態を避けるため、購入前の入念なレール確認は絶対に必要です。
2. 動作音が気になる?「キュルキュル音」の正体
次に多く聞かれるデメリットが、「動作音」です。「スイッチボット カーテン キュルキュル」という表現で語られることが多いこの音は、主に本体内部のモーター音や、レール上を車輪が走行する際に発生する摩擦音です。
特に静かな早朝や深夜にカーテンが自動で開閉すると、この動作音が思った以上に大きく感じられ、睡眠を妨げてしまう、あるいは気になってしまうという声があります。最新モデルの「SwitchBot カーテン3」では、静音モードが搭載され、旧モデルよりも動作音は大幅に改善されていますが、それでも完全に無音になるわけではありません。
音の感じ方には個人差がありますが、特に寝室への設置を考えている場合や、音に敏感な方は、この動作音がある程度発生することは覚悟しておく必要があります。レビュー動画などで実際の動作音を確認してみるのも良いでしょう。
3. スムーズに動かない?「引っかかる」「斜めになる」原因
「スイッチ ボット カーテン 引っかかる」「スイッチ ボット カーテン 斜めになる」といった、スムーズな動作ができないというトラブルも報告されています。これにはいくつかの原因が考えられます。
まず、「カーテンレールの歪みや段差、汚れ」です。レールが途中で曲がっていたり、繋ぎ目に段差があったり、ホコリや油汚れが付着していたりすると、SwitchBotカーテンの車輪がスムーズに走行できず、途中で引っかかったり、止まってしまったりします。レールの清掃やメンテナンスが重要になります。
次に、「カーテン自体の重さや生地の厚み」です。SwitchBotカーテンには対応できるカーテンの最大重量(例: カーテン3は約15kgまで)が定められています。特に重い遮光カーテンや、裏地付きの厚手のカーテンの場合、モーターのパワーが足りずに動きが遅くなったり、途中で止まったりすることがあります。「遮光カーテンがダメな理由は何ですか?」という疑問に対する一つの答えがこれです(重すぎる場合がある)。
また、取り付け時の「スイッチ ボット カーテン 高さ 調整」が不適切だと、本体が斜めになり、レールとの摩擦が増えて動きが悪くなる原因にもなります。
4. 意外なコスト?「両開き」と「ハブ」の必要性
SwitchBotカーテン導入の際には、本体価格以外にも考慮すべきコストがあります。まず、「スイッチボット カーテン 両開き」の場合、カーテンを左右両方に開閉させるためには、SwitchBotカーテン本体が「2台」必要になります。1台で操作できるのは片開きのカーテンのみです。これにより、導入コストが単純に倍になります。
さらに、SwitchBotカーテンの機能を最大限に活用するためには、「SwitchBotハブミニ」または「SwitchBotハブリモコン」といった、別売りの「ハブ」が必要になる点もデメリットと感じるかもしれません。SwitchBotカーテン本体とスマホはBluetoothで直接接続できますが、外出先からの操作や、アレクサ・Google Homeといったスマートスピーカーからの音声操作、タイマー設定の高度なカスタマイズなどを行うには、Wi-Fiに接続されたハブを経由する必要があります。
カーテン本体だけを購入しても、できることには制限がある、という点は理解しておく必要があります。(※最新モデルではハブ機能内蔵の製品も登場する可能性があります)
5. SwitchBotは中国企業?サポートやプライバシーは大丈夫?
「スイッチボットは中国企業ですか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。SwitchBotは、中国の深圳(シンセン)に本社を置く企業によって開発・販売されています。近年、スマートホームデバイスにおける中国企業の躍進は目覚ましく、SwitchBotもその代表格の一つです。
中国企業であることに対して、製品の品質や、日本語でのサポート体制、あるいは個人情報(プライバシー)の取り扱いについて不安を感じる方もいるかもしれません。品質については、初期不良や個体差の報告もゼロではありませんが、多くのユーザーレビューを見る限り、価格に対して十分な品質を持っていると評価されています。日本語のサポート窓口も用意されており、対応も比較的丁寧であるとの声が多いです。
プライバシーに関しては、スマートホームデバイス全般に言えることですが、利用規約やプライバシーポリシーを確認し、自身で納得した上で利用することが重要です。現時点では、SwitchBotが特に大きなプライバシー問題を起こしたという報告は少ないようです。
【2025年最新】デメリットを理解して選ぶ!SwitchBotカーテン&関連製品
 SwitchBotカーテンのデメリットを理解した上で、それでも導入したい!あるいは、代替となるスマートカーテンソリューションを探したい!そんなあなたのために、最新のSwitchBotカーテンと、関連する便利なスマートホーム製品をご紹介します。(※価格や在庫は2025年10月29日時点のものです)
SwitchBotカーテンのデメリットを理解した上で、それでも導入したい!あるいは、代替となるスマートカーテンソリューションを探したい!そんなあなたのために、最新のSwitchBotカーテンと、関連する便利なスマートホーム製品をご紹介します。(※価格や在庫は2025年10月29日時点のものです)
- SwitchBot カーテン 角型レール U型レール ポールタイ
- SwitchBot ハブミニ Matter対応 スマートリモコン
- +Style スマートカーテン
- めざましカーテン mornin’ plus (モーニンプラス)
- ニトリ 電動カーテンレール (※設置工事必要)
1. SwitchBot カーテン 角型レール U型レール ポールタイ
まずは本家、SwitchBotカーテンです。現在主流となっているのは「SwitchBot カーテン3」ですが、将来的に「スイッチ ボット カーテン 4」が登場する可能性もあります。購入の際は、必ずご自宅のカーテンレールの形状(U型、I型、ポールタイプなど)に対応したモデルを選んでください。これが「スイッチボット カーテン つけ られ ない」を防ぐ最大のポイントです。
カーテン3では、静音性能が大幅に向上し、「キュルキュル音」が気になるというデメリットが軽減されています。また、ソーラーパネル(別売り)を取り付ければ、充電の手間も省けます。最大15kgまでのカーテンに対応し、多くの家庭用カーテン(重い遮光カーテンも含む)を動かすパワーも備えています。
両開きの場合は2台必要になる点、フル機能を使うにはハブ(別売り)が必要になる点は依然としてデメリットですが、後付けでカーテンを自動化できる手軽さと、スマートホーム連携の豊富さは、他の製品にはない大きな魅力です。「スイッチ ボット カーテン デメリット」を理解した上で、それを上回るメリットを感じるなら、導入する価値は十分にあります。
2. SwitchBot ハブミニ Matter対応 スマートリモコン
SwitchBotカーテンの真価を発揮させるための「鍵」となるのが、このSwitchBot ハブミニです。これがないと、Bluetoothの届く範囲(家の中)からスマホアプリで操作するか、手動で少し引いて自動開閉させる(タッチ&ゴー機能)ことしかできません。
ハブミニをWi-Fiに接続することで、初めて「スマートホーム」としての機能が解放されます。外出先からスマホでカーテンを開閉したり、アレクサやGoogle Homeに「カーテンを開けて」と音声で指示したり、日の出・日の入りに合わせて自動で開閉するタイマーを設定したり。これらの便利な機能は、すべてハブミニがあってこそ実現します。
さらに、ハブミニは「スマートリモコン」としての機能も兼ね備えており、エアコンやテレビ、照明など、赤外線リモコンで操作する多くの家電を、スマホやスマートスピーカーから操作できるようになります。SwitchBotカーテンを導入するなら、このハブミニもセットで導入することを強く推奨します。Matter対応モデルなら、将来的なスマートホーム規格への対応も安心です。
3. +Style スマートカーテン
SwitchBotカーテンの対抗馬として、日本のプラススタイル社が提供するのが「+Style スマートカーテン」です。基本的な仕組み(カーテンレールに取り付けて自走する)はSwitchBotカーテンと同様ですが、いくつかの違いがあります。
+Style スマートカーテンは、本体にWi-Fi機能を内蔵しているため、SwitchBotのように別途「ハブ」を購入しなくても、単体で外出先からの操作や、スマートスピーカー(アレクサ、Google Home対応)との連携が可能です。これは大きなメリットと言えるでしょう。
対応レールもU型、I型、ポールタイプと幅広く、取り付け方法もSwitchBotと似ています。動作音やパワー(対応重量)については、レビューなどを比較検討する必要があります。価格帯もSwitchBotカーテン(+ハブミニ)と同等か、やや高めになる場合がありますが、「ハブ不要」の手軽さを重視するなら、有力な選択肢となります。「スイッチ ボット カーテン デメリット」であるハブの必要性を解消してくれるモデルです。
4. めざましカーテン mornin’ plus (モーニンプラス)
後付け型スマートカーテンの先駆けとも言えるのが、ロビット社の「mornin’ plus (モーニンプラス)」です。SwitchBotカーテンと同様に、カーテンレールに取り付けて使用します。
mornin’ plusの特徴は、そのシンプルな機能と、比較的安価な価格設定にあります。スマホアプリ(Bluetooth接続)からタイマー設定が可能で、指定した時間に自動でカーテンを開閉させることができます。太陽の光で自然に目覚めたい、というニーズに特化しています。
ただし、SwitchBotや+StyleのようなWi-Fi接続機能やスマートスピーカー連携機能は基本的にありません(※別売りの連携デバイスが必要な場合あり)。あくまでスマホが近くにある範囲での操作と、タイマー設定がメインとなります。また、対応レールやパワー(カーテン重量)にも制限があるため、購入前の確認は必須です。シンプルな機能で十分、とにかく安価にカーテンの自動開閉を実現したい、という場合に検討の価値があります。
5. ニトリ 電動カーテンレール (※設置工事必要)
「スイッチ ボット カーテン 引っかかる」「斜めになる」といった動作の不安定さがどうしても許容できない、もっと確実で静かな自動開閉を求めるなら、最終的には「電動カーテンレール」への交換が最も確実な解決策です。ニトリなどでは、後付け可能な電動カーテンレールの設置サービスを提供しています。
これは、SwitchBotのように既存のレールを使うのではなく、モーターを内蔵した専用のカーテンレール自体を設置する方式です。そのため、レールの形状に悩む必要がなく、動作音も非常に静かでスムーズ。カーテンの重さにも余裕を持って対応できます。リモコンや壁スイッチで操作するタイプが主流ですが、スマートホーム連携が可能なモデルも登場しています。
最大のデメリットは、設置に「工事」が必要であり、費用もSwitchBotカーテンの数倍以上かかる点です。賃貸住宅では大家さんの許可も必要になります。しかし、一度設置してしまえば、後付けデバイス特有のトラブルとは無縁の、最も安定した快適な自動カーテン環境を手に入れることができます。「スイッチ ボット カーテン デメリット」を根本から解決したい場合の、究極の選択肢と言えるでしょう。
まとめ:デメリットを理解し、後悔のないスマートカーテン選びを
 スイッチボットでカーテン開閉を自動化するデメリットとして、対応レールの制限、動作音、引っかかりのリスク、追加コスト(両開き、ハブ)などが挙げられました。これらの点を理解し、自宅の環境(レール形状、カーテン重量)を事前にしっかりと確認することが、導入後に後悔しないための最も重要なステップです。
スイッチボットでカーテン開閉を自動化するデメリットとして、対応レールの制限、動作音、引っかかりのリスク、追加コスト(両開き、ハブ)などが挙げられました。これらの点を理解し、自宅の環境(レール形状、カーテン重量)を事前にしっかりと確認することが、導入後に後悔しないための最も重要なステップです。
SwitchBotカーテンの手軽さは大きな魅力ですが、ハブ不要の+Styleや、よりシンプルなmornin’ plusといった選択肢もあります。そして、確実性や静音性を最優先するなら、電動カーテンレールへの交換も視野に入れるべきでしょう。
カーテンの自動開閉は、日々の生活を確実に便利で快適にしてくれます。この記事で紹介した情報が、あなたのライフスタイルに合った、最適なスマートカーテン選びの一助となれば幸いです。